





『アイアン型UT』
この名前を聞くと、
なんてイメージを持つ方が多いでしょう。
しかし、今日その固定概念はすべて忘れて、
この先のお手紙を読んでください。
これからご紹介するアイアン型UTは、
ロングアイアンの代わりに採用したり、
一部の人にしか扱えないような
難易度の高い一般的なアイアン型UTとは全くの別物。
あなたのセカンドショットや
サードショットでグリーンを捉えるための、


ウェッジでならグリーンに載せられるけど、
ショートアイアンやミドルアイアンでは
乗ってもグリーンの端か、刻むので精いっぱい…
そんな悩みを持つゴルファーに対して
日本の地クラブメーカーが導き出した最適解が、このクラブなんです。
それではこのクラブの紹介をする前に、
現代のアイアンが抱える問題、そして
プロ達が見据えている未来のクラブセッティングについて、
お話させていただきます・・・


一般ゴルファーの永遠の悩みの一つが「飛距離」。
アイアンは飛距離を求めるよりも
安定性を重視するクラブですが、
その飛距離が落ちてくれば
当然グリーンを正確に狙える
射程も短くなるということなので、
スコアメイクにとっては死活問題。
その結果、
現代のアイアンは安定性とともに
その飛距離性能も大幅に向上してきました。
そんな時流の中で、
近年ではアイアンのストロングロフト化が進んでいます。
例えば一般的なアイアンのロフト角というと、
60年前なら5番で32°、Pwで52°でした。
現代であれば、5番で25°、Pwで44°程度でしょう。
当時と比較すると
ちょうど番手が2つ違ってくるくらい、
現代のアイアンのロフトは立っている、ということです。


もちろん、この背景にはクラブ製造技術が進歩して球が上げやすくなったり、
AwやGw、60°の高ロフトウェッジなどウェッジ周りの本数を細かく増やして
ショートゲームの精度を上げるセッティングの変化なども影響しています。
ですが現代のストロングロフト化が進んだ結果として、
ヘッドスピードが低いゴルファーには
低くてランが多いショットになりやすい。
という問題が起こっているのです。


筋力の低下とともにアイアンの飛距離が落ちているゴルファーにとって、
ランが多くても飛距離が出るのは一見救いのように思えますが、
大きな問題があるのです。
それは、
ストロングロフトでも、
特に大手のツアーモデルのアイアンなどが顕著ですが、
ある程度のヘッドスピードが無いと球が上げられないような設計の物が多いです。
そうすると、一見して好条件での総飛距離は
球が高く上がるアイアンと同等程度に見えても、
その中身はキャリーが短く、ランによる距離の割合が大きくなります。
そうすると、芝やライの状況次第で飛距離の影響を受けやすく、
傾斜や雨、芝の長さなどコースコンディションによって
飛距離が落ちてバラバラになり、不安定になりかねません。
キャリーの差も小さくなるため、
ランが出にくい状況では番手ごとの飛距離の差も縮まり、
番手を上げたのに届かない、という場面も出てきます。


さらに悪いことに、
ランの割合が増えるということは
グリーンに乗せにくいという
問題も抱えているということです。
グリーンはコース内で最も芝が刈り込んであり、
転がりの良いシチュエーションです。
しっかり高さが出て止まるボールなら
狙ったところにとめやすいですが、
ランの割合が大きいということは
グリーン上で転がる距離も比例して伸びるということ。
そうすると当然転がりの距離は伸びてしまい
オーバーしてしまう確率も爆発的に上がるし、
距離のコントロールも難しくなってしまいます。


 特に砲台グリーンや高低差がある場面では、
特に砲台グリーンや高低差がある場面では、
手前に打てば傾斜でショート、
傾斜を越えれば大オーバーなど、
グリーンに残すこと自体が困難
という場面も出てしまいます。

結果、球が低く打ち出されやすくなり、
ランが出にくい状況では各番手の飛距離の差が出にくく
高さで止まらないためグリーンに残りにくい
という結果に繋がってしまうのです。
しかし、
そんな悩みを抱えた
シニアゴルファーのために開発されたのが、
今回ご紹介する“高ロフトUT”。
ミドル・ショートアイアンの役割をもっと簡単にこなせる、
新時代のユーティリティなんです。
今ではアイアンは5番・6番からPwまでがセットで販売されているのが一般的ですから、
一見、ミドル・ショートアイアンの高ロフト帯までユーティリティに任せるというのは
風変りにも思えるかもしれません。
しかし実は、
プロのフィッターはこの新時代のクラブを「予言」し、
プロゴルファーでは既に導入もされていたのです・・・


ユーティリティがクラブの中での役割を拡大していくことは、
プロゴルファーやプロフィッターの中では既に認知されてきた事実なのです。
「フォーティーン」の設立者であり、「重心距離」や「重心深度」など
現代のクラブのスペックでは常識になっている概念をクラブ設計に導入した第一人者であり、
データによるクラブ設計を確立させたクラブフィッターのレジェンドである故・竹林隆光氏。
彼は、将来のクラブセッティングは
アイアンの役割をユーティリティが担っていくことで、


と、現代のアイアンのストロングロフト化と、
ユーティリティの進化によってその役割が増えていくであろうことを「予言」していたのです。
 その予言を現実にするかのように、
その予言を現実にするかのように、
去年のレギュラーツアーで、片山晋呉プロが
7番アイアンを抜いて7番のUTを使用したことで
話題になっていました。

今では女子のツアープロでも
“UTのショート番手化”が進行中です。
つまりこのクラブは、クラブの進化を予見したクラブ作りのプロが予見し、
現役のプロにも浸透しつつある未来の常識を先取りした一本なのです。
ただ、プロのようにウッド型UTで曲がらない正確なショットを打つのは、
難易度が高いと感じる方も多いでしょう。
そこでその両面の良いとこどりをするのが、
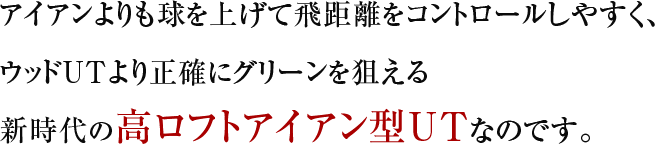

しかし実は今回ご紹介するこのUT、
もともとはそこまで高ロフトの役割を担わせる目的で開発された物ではなかったのです。
それはシニアゴルファーの願いから生まれた、偶然の産物でした。


従来のユーティリティといえば、
3番や4番のロング番手の代替品として扱われることが主流ですよね。
実は今回のアイアン型UTも、
最初はロング~ミドルアイアン程度を代用する目的で製造されており、
高番手のロフトも今でも人気を博しています。
当初はロフト角21°~27°といった、
アイアンの番手出言えば3番~6番くらいの役割をもつ
ロフトのアイアン型UTとして製造されました。
しかし、実際に使用したゴルファーから、
こんな要望があったのです・・・

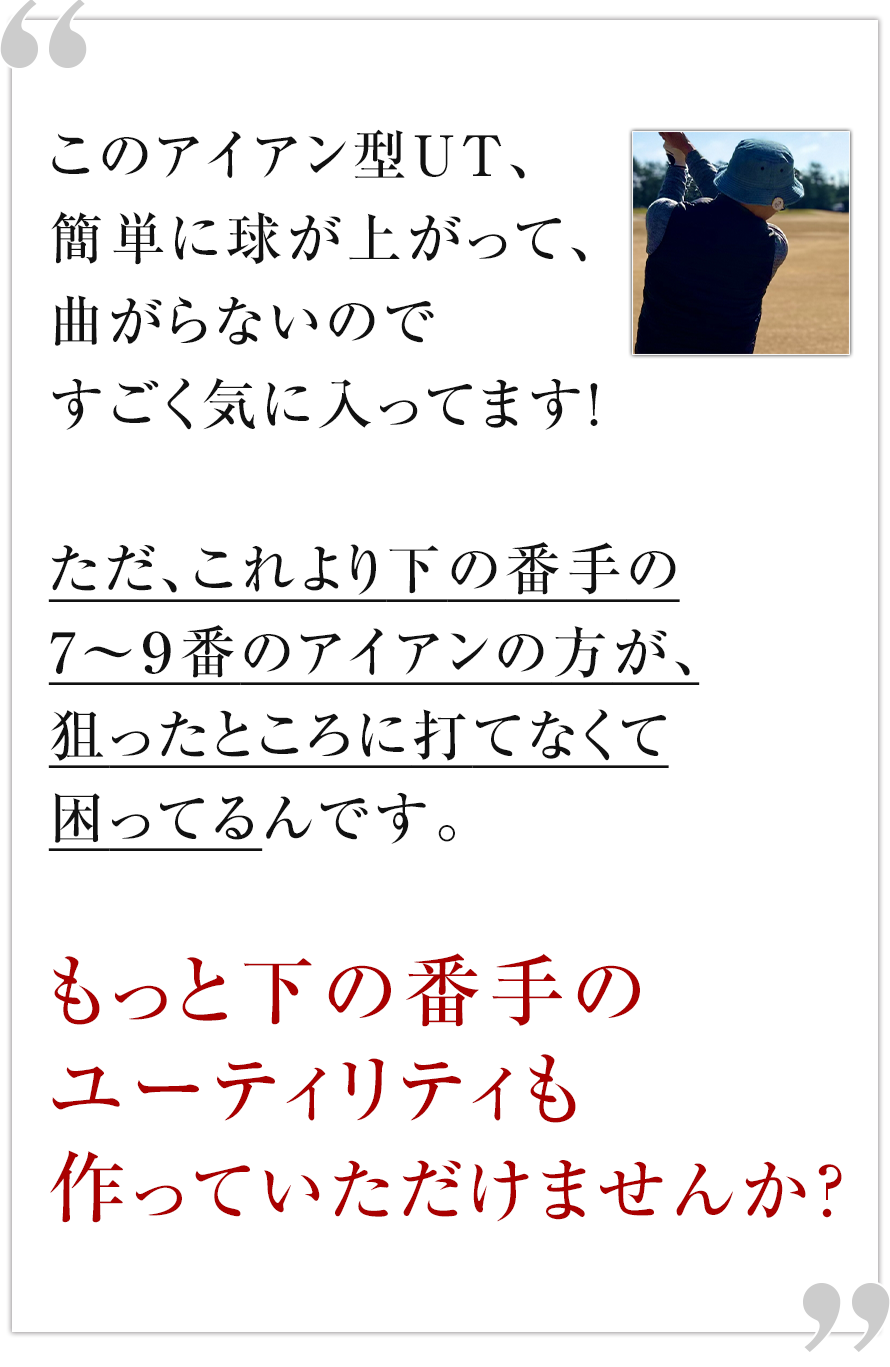
このアイアン型UTを気に入っていたお客様の中で、
何と下の番手までユーティリティで固めたい、
という要望が多数届いたのです。


この声が、すべてのはじまりでした。
日本の地クラブメーカー「フライハイト」は、
その言葉に真剣に向き合い、“番手の再設計”を決意したのです。


シニアでも「刻む」という選択肢から、
グリーンを「狙う」ための攻めのゴルフを諦めないための、
新時代のクラブの誕生でした。


 アイアン型UT。
アイアン型UT。
こう聞くだけで、
「難しそう」「使いこなすのが大変」
そう身構える人も多いと思います。

通常、ユーティリティといえば3~5番のロング番手ですが、
今回ご紹介するGXDハイブリッドは、7番・8番・9番相当の“高ロフトUT”。
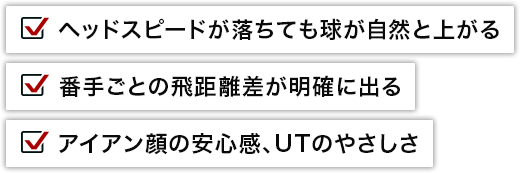

この“高ロフトUT”が、
グリーンを正確に狙い、止め、スコアを変えてくれます。


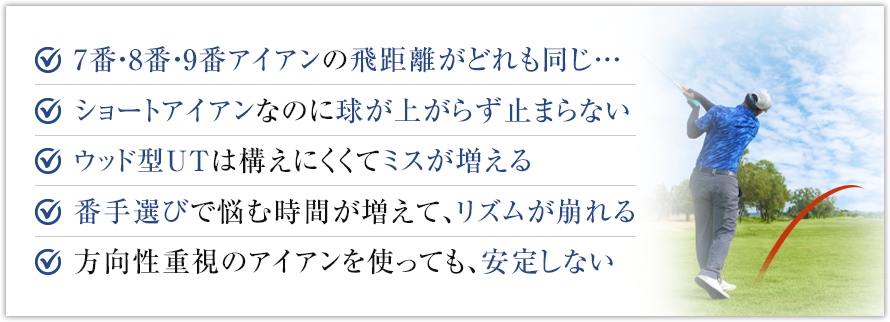

あなたがもつ悩みはすべて、
現代アイアンのストロングロフト化がもたらしたクラブの問題かもしれません。
だからこそ・・・


このUTは、ストロングロフト化で失われた
「打ち出し角」「高さ」「キャリー」「番手差」を取り戻す設計。






 番手ごとにキャリーの差がハッキリ出るので、
番手ごとにキャリーの差がハッキリ出るので、
7番、8番、9番と番手ごとの距離の階段が明確に。
距離のブレがなくなり、クラブ選択に迷わなくなります。



「高さが出ない…」「止まらない…」を克服。
スピン性能にも優れており、
ウェッジ以外でもピンをデッドに攻められる武器に。


高慣性モーメント設計で、安定した直進性を発揮!
フェースコントロールも安定するため、
球の曲がりが少ない、真っすぐ狙いたいゴルファーにピッタリです。


アイアンの顔で構えられるため違和感ゼロ。
地面からでもティーアップでも構えやすく、
「打てそうな気がする」自信がスイングを変えます。


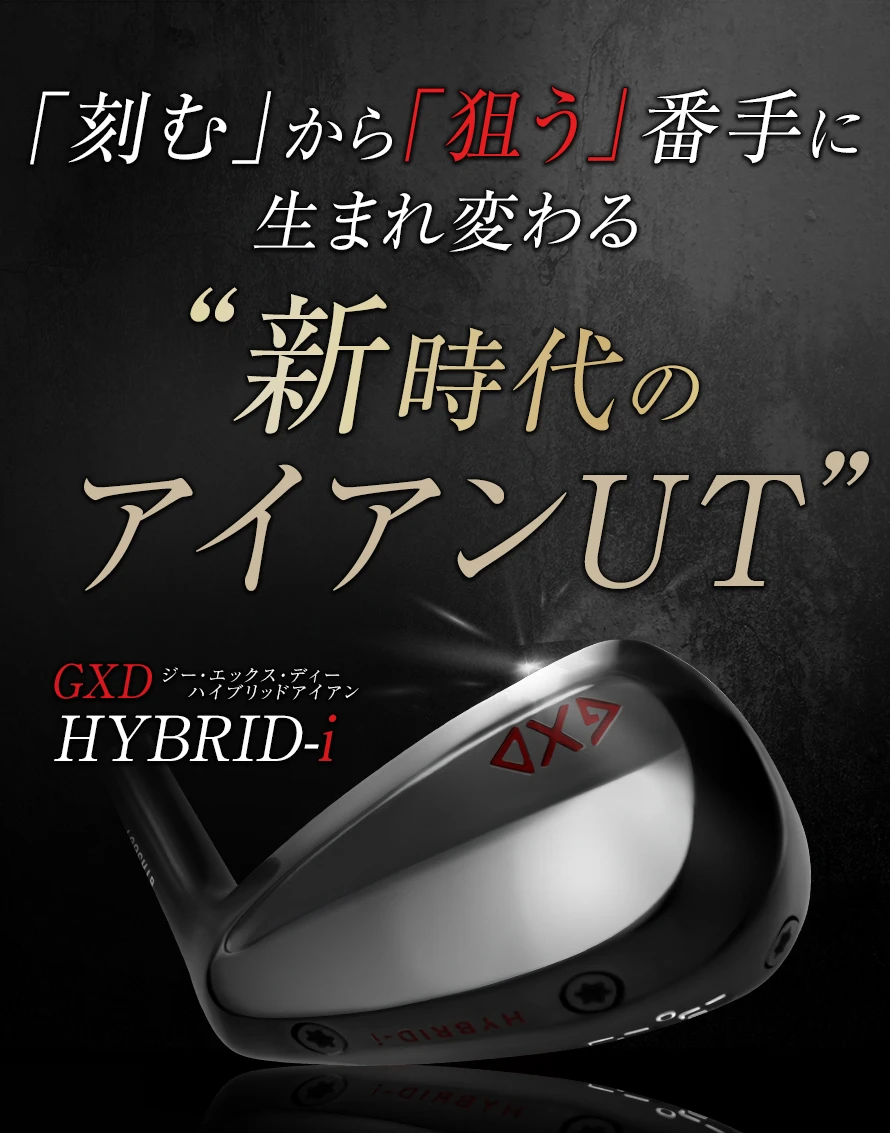

一般的なUTは#3〜#5(ロフト18〜24°程度)が中心ですが、このGXDハイブリッドは#7(27°)~#9(41°)という高ロフトUTゾーン設計。

近年のアイアンのストロングロフト化によって球が上がりにくく、ヘッドスピードが落ちるにつれてグリーンへ乗せることが難しくなる問題を完璧にサポート。
「高く上げて、ピンを狙いたい」
「弁手ごとの飛距離の差が出にくくなった」
「アイアンが打てなくなってきたけど、ウッド型ではなくアイアンの顔で構えたい」
そんなゴルファーにとって、他にはない唯一無二の存在です。

フェースには高強度「カスタム455マレージング」をL(エル)型カップフェースで採用。
カップフェース特有の広いスイートエリアによって、普通のアイアンよりもミスを軽減。

見た目にはシャープながら高い慣性モーメントを持っているため、フェースコントロールも安定しやすく、直進性の高いショットをサポートしてくれます。

ヘッド全体が光沢を抑えたブラック加工で反射を抑えて視認しやすく、一方でスコアラインの最下段だけをホワイトラインとすることで視覚的にスクエアに構えやすくなっています。

ネック形状もほぼストレートなため感覚的にもアドレスしやすく、視覚的にも構造的にもスクエアに構えやすい直進性に特化した設計となっています。

ソール幅もアイアン型ハイブリッドにしては抑えめで、全体的に広いというよりヘッド後方にボリュームを持たせており、このソール形状が抜群の抜けの良さと、インパクト時にボールを押し出すギア効果で飛ばしを強化します。

一般的な「タラコ型」のハイブリッドは見た目が大きく違和感を持つ方も多いですが、このGXDハイブリッドはサイズもコンパクトな上、ヘッド全体がシャープに見えるブラックIP加工で仕上げてあるので、構えるときもアイアンと近い感覚で構えることができます。

しかしコンパクトな見た目に反してソール後方(3g×2箇所)とトゥ側(5g×1箇所)に可変式ウェイトビスを装着されているため重心はアイアンよりも深い低重心の設計。

この低重心設計によりミスショットへも強く、ヘッドスピードが落ちてきても飛距離と球の上がりやすさを強化してくれます。

GXD HYBRIDに最適な組み合わせを導き出すため、プロのクラブフィッターに依頼し、このハイブリッドと最も相性が良く、重量・バランスも最適なシャフトを選定。
その結果選ばれたのが、日本でも屈指のシャフトメーカーである「コンポジットテクノ社」の代表シリーズ Fire Express(ファイアー・エキスプレス)からSpirits(スピリッツ)シャフト。

その大きな特徴は、シャフトの外層に四軸組布シートを組み込んだ独自のテクノロジーによって強化された独自のしなりテクノロジーを搭載したカーボンシャフトであること。
スピリッツには重量帯での種別分けがありますが、外層の剛性が増せばシャフトの挙動も安定し、しなりの性能を重量帯ごとにより自由に設計できるため、タイミングが取りやすくカーボンシャフトの恩恵も存分に得られます。
今回はヘッドとの相性を考えて軽量のi50シャフトを選定しました。
重量帯ごとの種別のためフレックスの差分はありませんが、フレックスでいうならばR~SRに相当するシャフトで、ヘッドスピードで30m/s台~40m/sほどの方に最も適しているシャフトです。
安定したしなりの良いシャフトといっても、先述のテクノロジーのおかげで安定したインパクトと振り抜きの良さは健在。
ボールのつかまりと弾道の高さ、そして飛距離と方向性の安定を強化してGXDハイブリッドの長所をより際立たせてくれます。

今回装着したのは、
ヘッドに合わせてFREIHEIT社のFREIHEITブランド完全オリジナルラバーグリップ。

ソフトフィーリングながら抜群のホールド感で、
ソフト感のある素材ABRを使用しながらオリジナルXパターンが抜群のホールド感を実現。
製造は茨城県の芹沢ゴム工業。
完全国内生産で、日本人の手のサイズや湿気など気候も考慮して作られた
THE-Gブランドの良さを最大限引き出すグリップです。
クラブとの唯一の接点であるグリップを通じて、
手から腕へ、腕から肩へとあなたが最もリラックスした状態で、
力みのないしなやかなスイングが可能となり、
確かな飛距離アップを手元からサポートします。




 以前は130y以上の番手は高さが出にくかったので、寄せられてもグリーンに乗るイメージが持てなかった。もしくはガードバンカーに捕まるかの不安しかなかった。
以前は130y以上の番手は高さが出にくかったので、寄せられてもグリーンに乗るイメージが持てなかった。もしくはガードバンカーに捕まるかの不安しかなかった。

 ラウンドで少しでも傾斜がある場面だと、練習のように打てずに番手ごとの飛距離差も出にくくて番手選びに悩んでいました。
ラウンドで少しでも傾斜がある場面だと、練習のように打てずに番手ごとの飛距離差も出にくくて番手選びに悩んでいました。









このハイブリッドは、一般的なハイブリッドとは全く異なる役割をもった物です。
そのすべてが、このハイブリッドに詰まっています。


今回、このハイブリッドにはクラブ調整の
トータルサポートをお付けしています!
シャフトや重量の調整なども含めて、後から調整したいと考えた時に、
このクラブについて熟知して、ベストな提案をくれるクラブフィッターがいたら心強いですからね。
さらに、このトータルサポートは
このハイブリッドだけに限ったものではありません。
このハイブリッドはクラブセット内でスコアメイクの中核を担う
「得意クラブ」として重要な立ち位置になると考えています。
「得意クラブ」とは、
単にそのクラブのショットの結果が安定している、というだけでなく、
スイングを安定させるための感覚の基準となり、
そのクラブを中心にマネジメントを
組み立てることでスコアを安定させるなど、
ゴルフ全体の軸となるクラブの事です。
通常ピッチングウェッジ~7番アイアンくらいの飛距離のクラブで軸となる得意クラブを作ると、
ショート・ミドル・ロングホールなど全コースのマネジメントで活用しやすいとされます。
そう、、、まさに、このハイブリッドが担う役割にピッタリ符合するんです。
そうした時に、アイアンやハイブリッドというのは、
クラブセット全体の重量や「流れ」も大切です。
それゆえに、使っていくうちに今回のハイブリッドを中心にクラブセットを再構築して、
他のアイアンなどでも違うシャフトを試したくなるかもしれません。
このハイブリッドは勿論、
クラブセット全ての性能を十全に発揮してスコアメイクに繋げて頂きたいのです。
 そこで、このGXDハイブリッドだけでなく、
そこで、このGXDハイブリッドだけでなく、
それ以外のクラブセッティングを含む
購入後のクラブ調整やシャフト交換など、
あらゆる悩みに対して経験豊富な
プロのフィッター・クラフトマンへの
相談依頼が可能なトータルサポートをお付けいたします!

クラブセットに関する相談をお受けし、
ご希望の方には今回のハイブリッドを知り尽くしたクラフトマンが
直々にそのクラブの調整作業を請け負います。
※作業や送料が発生する場合、初期不良等を除いて費用はお客様のご負担となります。


 今回のアイアン型ハイブリッドは、
今回のアイアン型ハイブリッドは、
ヘッドスピードが落ちてきた方や、
アイアンの精度に自信がない方にとって、
既存のハイブリッドとは一線を画す“武器”になるはずです。

7番・8番・9番のポジションを
このハイブリッドに置き換えるだけで、
ミドル〜ショートアイアンの悩みをまとめて解決。
セッティングもシンプルになり、ウェッジとウッド以外をたった3本でまかなえる
まさに“次世代の番手構成”が実現します。
もし、同じような役割を既存のアイアンセットで代用しようと、
地クラブメーカーでオーダーした場合は20万円近くなることも珍しくありません。
しかも今回は、
と、破格のトータルサポート付き。
それを考えれば、20万円以上の価値があるといっても過言ではありません。
トータルサポートなどを除いたとしても、
このクラブの定価は公式サイトのオンラインショップでも、
カーボンシャフトでセッティングを組めば確実に5万円以上の価格はついていますし、
シャフトによっては送料込みで1本当たり
定価56,250円
3本セットでなら
定価168,750円で販売されているハイブリッドです。
しかし今回、ミドル・ショートアイアンのハイブリッド化という新たな可能性を切り開くにあたり、
ゴルフライブとしてコスト面も全面サポートさせていただきます!
具体的には、送料はすべてゴルフライブが負担。
さらに、プロフィッターの方と選定したカーボンシャフト、
メーカーのオリジナルグリップといったパーツも全て特別割引として、
クラブのトータルサポートを無料でお付けしたうえで…
1本当たり
定価45,000円(49,500円・送料無料)でご用意します。
さらに3本セットでならさらにセット割引で、
特別割引132,000円(145,000円・送料無料)。
これはゴルフライブ読者限定・完全非公開の特別案内です。
次回、この価格でご提供できるかどうかはまったくの未定。
今回が“最初で最後のチャンス”になる可能性もあります。


あまりの反響に、初回で販売した20セットは1日と持たずに完売してしまいました。
「いくらなんでも早すぎる」
「GWでメールを確認出来ていなかった」
そんなお問い合わせも殺到したため、
急遽メーカーに依頼し、他の工房に出荷予定だった
入荷待ちのヘッドを特別に融通してもらい、
追加で6セットだけご用意できることになりました。
今回確保できたヘッドは今まさに入荷待ちの状態で、
そこからクラフトマンがバランス・重量を調整しながら組み立てを行うため、
発送までは約3週間ほどお時間をいただきます。
それでも、
という、他では手に入らないクオリティのクラブをお届けできることはお約束します。
ただし、今回の6セットが完売した後、次回製造の見通しはまだ立っていません。
それどころか、入荷したとしても最近の物価上昇のあおりを受けて今後価格が上がる可能性すらあります。
いま、この条件で手に入れられるのは完全な早い者勝ちですので、今すぐ詳細をご確認ください。






| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | 長さ(インチ) | 総重量 (数gの交差あり) | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 27° | 61.5° | 261g | 37.75 | 362g | C8 |
| #8 | 34° | 62° | 270g | 37.0 | 371g | |
| #9 | 41° | 63° | 280g | 36.25 | 381g |

| シャフト重量 | フレックス | キックポイント |
|---|---|---|
| 50g | ワンフレックス(R~SR相当) | 中調子 |
※7~9番はヘッドスピード40m/s未満の方にオススメです。

| 重量 |
|---|
| 49g ±2g |
各番手を単品でご注文をご希望の方は、こちらからご注文ください>>
(セット割引は適用外となります。)
また、より高い番手の5、6番をお求めの方は詳細をこちらからご確認できます>>
※7~9番はヘッドスピード40/s未満の方に特にオススメしておりますが、
5,6番はヘッドスピード42m/s以上の方にオススメしております。








| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | 長さ(インチ) | 総重量 (数gの交差あり) | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 27° | 61.5° | 261g | 37.75 | 362g | C8 |
| #8 | 34° | 62° | 270g | 37.0 | 371g | |
| #9 | 41° | 63° | 280g | 36.25 | 381g |

| シャフト重量 | フレックス | キックポイント |
|---|---|---|
| 50g | ワンフレックス(R~SR相当) | 中調子 |
※7~9番はヘッドスピード40m/s未満の方にオススメです。

| 重量 |
|---|
| 49g ±2g |
各番手を単品でご注文をご希望の方は、こちらからご注文ください>>
(セット割引は適用外となります。)
また、より高い番手の5、6番をお求めの方は詳細をこちらからご確認できます>>
※7~9番はヘッドスピード40/s未満の方に特にオススメしておりますが、
5,6番はヘッドスピード42m/s以上の方にオススメしております。
会社概要 | 特定商取引法上の表記 | プライバシーポリシー | TOPへ
会社概要 | 特定商取引法上の表記 | プライバシーポリシー | TOPへ